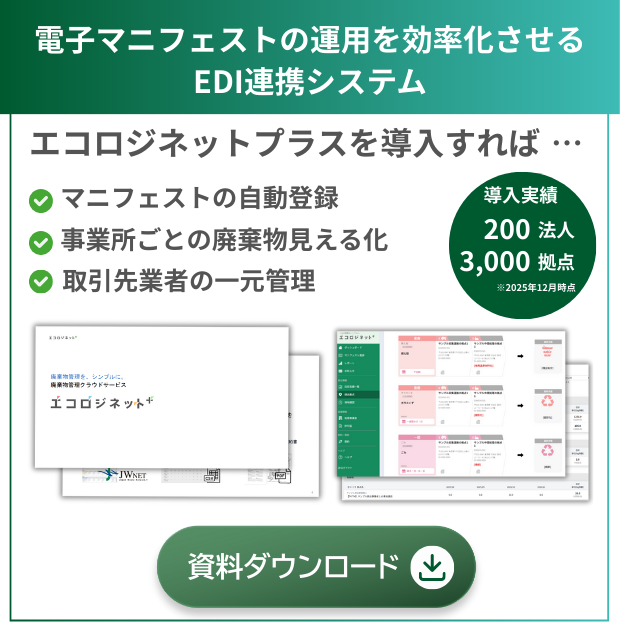地球温暖化対策 GHGの削減とその取り組みについて
近年、「過去最高気温」や「最大級の台風」といった言葉をニュースで耳にすることが増えました。
異常気象はもはや特別な出来事ではなく、私たちの身近で繰り返し起きています。こうした異常気象の背景には地球温暖化があり、その温暖化を進めている大きな要因が GHGの増加です。本記事では、GHGの基礎知識から、Co2との違い、GHG削減が求められる背景や具体的な取り組みまでを解説します。
環境問題に関心のある方はもちろん、基礎的な知識を整理したい方にも役立つ内容になっています。
目次
GHG(温室効果ガス)の基礎
GHGとは
GHGとは「Greenhouse Gas(グリーンハウスガス)」の略称で、日本語では「温室効果ガス」と呼ばれます。名前の通り、温室のように地球の大気に熱をため込み、気温を上昇させるはたらきを持つガスの総称です。GHGは本来、地球を寒さから守る大切な役割を担っています。もし温室効果ガスがなければ、地球の平均気温はマイナス18℃程度になり、生物が生存できなくなってしまいます。つまり、私たちが暮らしていけるのは適度な温室効果のおかげであり、温室効果ガスがまったくなくなればよいというわけではありません。しかし、産業革命以降、人間の活動によってGHGが過剰に排出されるようになり、地球の気温が上がりすぎる「地球温暖化」が深刻な問題となっています。
GHGを構成する主なガス
GHG(温室効果ガス)は複数のガスの総称です。構成するガスの種類は、以下の通りです。
二酸化炭素(CO2):化石燃料の燃焼(発電、輸送、工場活動など)で排出される。GHGの7割を占める。
メタン(CH4):家畜のゲップや稲作、廃棄物処理から発生する。
一酸化二窒素(N2O):農業の化学肥料や工業プロセスから発生する。
HFC:冷蔵庫やエアコンの冷媒として利用される。
PFC:半導体製造や工業プロセスで使用される。
SF6:半導体製造や工業プロセスで使用される。
NF3:半導体製造や工業プロセスで使用される。
これらのガスは濃度や排出量が異なりますが、いずれも温室効果をもたらすため、まとめて「GHG」と呼ばれています。
GHGとは?CO2との違い
では、「GHG」と「CO2」は同じものなのでしょうか?答えは 「CO2はGHGの一部」 です。
GHGは温室効果ガス全体の総称であり、世界の温室効果ガス排出量のうち 約7割をCO2が占めるといわれているため、「温室効果ガス削減=CO2削減」と表現されることが多いです。また、メディア報道においても、一般的に分かりやすい表現として「CO2」と表現されるケースもありますが、国際的な削減目標ではCO2以外のガスも含めた「GHG」と表現されます。
GHG削減が必要になった背景
気候変動の深刻化
地球の気候はもともと長い期間の中で変動してきましたが、産業革命以降、化石燃料の大量燃焼や工業活動の拡大により、温室効果ガスの濃度が急速に増加しました。現在では、類を見ない速さで地球の平均気温が上昇し、猛暑・豪雨・干ばつ・海面上昇など生態系への影響が深刻な問題となっています。また、IPCC※1で示されたRCPシナリオ※2では、地球の平均気温は最大4.8℃上昇すると予測されています。このままGHGの削減を行わなければ、さらに私たちの生活に影響が出ると考えられます。
※1 IPCC(気候変動に関する政府間パネル):世界気象機関(WMO)及び国連環境計画(UNEP)により1988年に設立された政府機関
※2 RCPシナリオ:IPCCが提唱した、将来の温室効果ガス濃度の変化を想定した「代表濃度経路」
国際的な枠組み
このような状況から、このままでは気候変動の影響が世界中で深刻化するため、GHG削減に向けた国際的な取り組みが進められるようになりました。その代表的なものの一つが「京都議定書」です。1997年に京都で開催された国連気候変動枠組条約第3回締約国会議(COP3)にて採択され、先進国に対して初めて温室効果ガスの削減が義務化されました。具体的には、各国は1990年を基準年として、GHG排出量を一定割合削減することが求められ、各国では法整備や削減策が実行されました。また、2015年には、パリ協定にて、全世界を対象に「世界の平均気温上昇を産業革命以前に比べて2℃より十分低く保ち、1.5℃に抑える努力をする」という国際的な枠組みが定められました。これにより、世界中のすべての国は「削減目標(NDC)の提出」と「進捗を5年ごとに更新・報告すること」が義務化されています。
日本におけるGHG削減の取り組み
国の方針
日本は2020年に、パリ協定に基づき、「2030年までに2013年度比で46%のGHG削減」を国際的に約束しています。また、同年には日本独自の長期ビジョンとして2050年までに温室効果ガスの排出を実質ゼロにすることを目標とした「2050年カーボンニュートラル」を宣言しました。
具体的な施策
再生可能エネルギーの拡大:太陽光、風力、地熱、バイオマスなどの導入を加速
省エネ・電動化の推進:ZEB(ゼロエネルギービル)、EV(電気自動車)、省エネ家電の普及
カーボンプライシングの導入検討:炭素税や排出量取引制度による経済的なインセンティブ
企業・自治体の取り組み
企業はTCFD※1に基づき気候関連リスクを情報開示
サプライチェーン全体でGHGを把握する動きが進展(Scope1,2,3)
自治体も「ゼロカーボンシティ」を宣言し、地域ごとの取り組みを展開
このように、国・企業・自治体がそれぞれの立場で削減努力を進めています。
※1 TCFD(気候関連財務情報開示タスクフォース)は、気候変動が自社の事業に与えるリスクや機会をどう考え、どう対応しているかを開示すること
5. まとめ
GHG(温室効果ガス)はCO2をはじめとする複数のガスから成り立ち、地球温暖化の大きな要因とされています。近年では、国や企業によるGHG削減の取り組みが加速していますが、その中で見落とされがちなのが廃棄物処理に伴うGHG排出です。廃棄物の処理の過程において温室効果ガスが発生しており、排出事業者・処理業者の双方にとって、GHG排出量の可視化と削減への取り組みが欠かせません。
当社では、廃棄物処理におけるGHGの「見える化」や削減のご支援を行っております。関心のある方は、ぜひお気軽にご相談ください。
カテゴリー別に記事を探す
キーワード別に記事を探す
CONTACT
お問い合わせ
廃棄物の処理・管理、
資源の再利用に関する課題をお持ちの企業様
まずはお気軽に
お問い合わせください
まずは貴社の課題をお聞かせください。最適なプランをご提案をさせていただきます。
無料でお見積りも承ります。