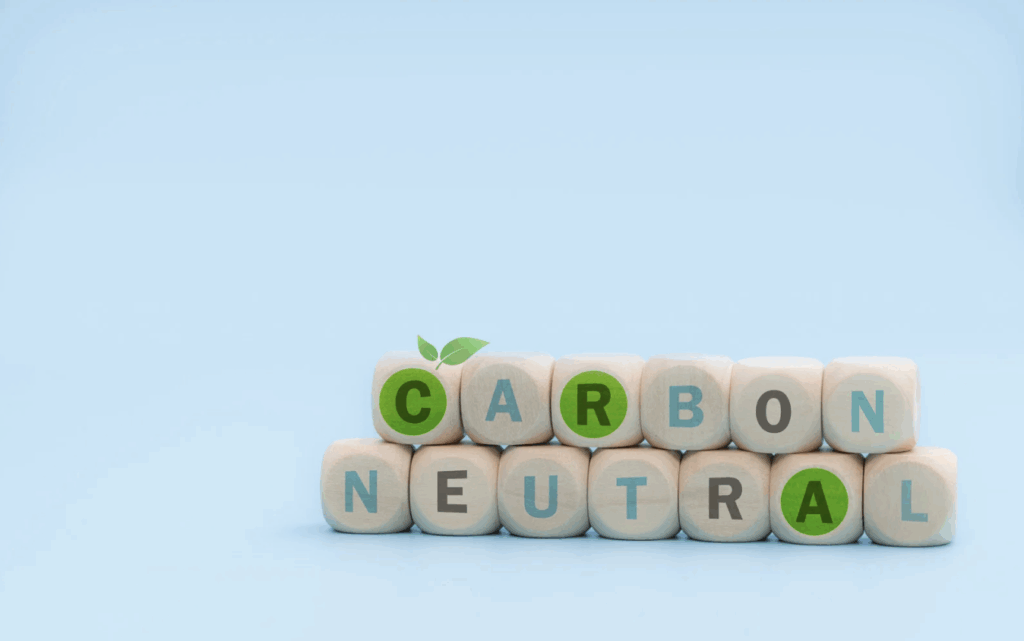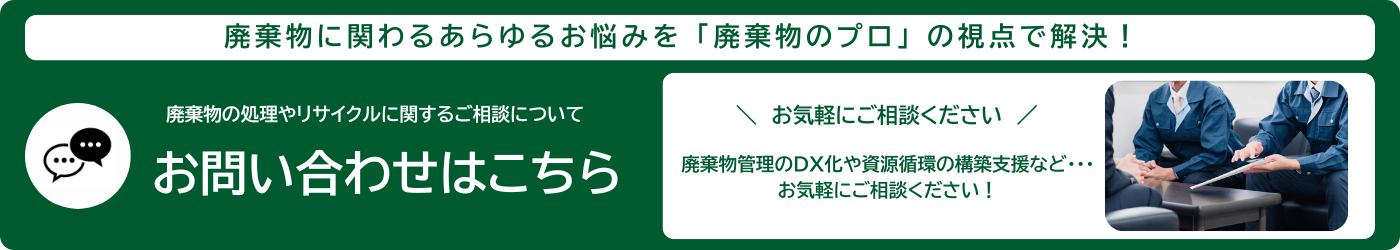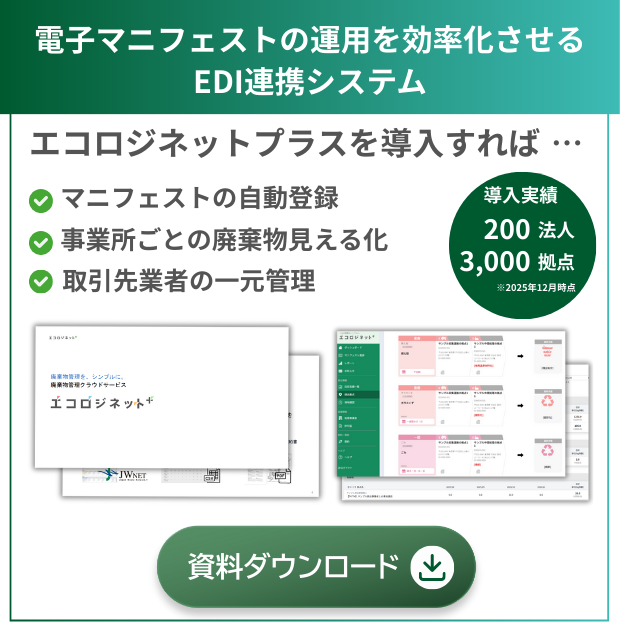カーボンニュートラルの実現に向けて
–有効的な取組の定着化のため企業が取るべき対策-
今や世界中で「カーボンニュートラル(温室効果ガスの排出実質ゼロ)」への取り組みが必須となっています。
気候変動への対応は環境問題の枠を超え、経営リスクであり、同時に成長機会でもあるテーマとして位置づけられるようになりました。
本稿ではより実践的に取り組むことで生まれる企業側のメリットについて解説します。
目次
1.はじめに ― 「脱炭素」はもはや企業経営の新しい常識
2015年に採択されたパリ協定に則り、カーボンニュートラル社会の実現は世界共通の長期目標として各国で様々な取り組みがなされています。日本も2020年に「2050年カーボンニュートラル宣言」を表明し、2050年までにCO₂の排出を実質ゼロにするという目標を掲げました。※1
この目標達成には、温室効果ガスの排出量の削減やエネルギー転換、再エネ導入等だけでなく、産業構造そのものの転換が求められています。特に廃棄物処理やリサイクル業界は、温室効果ガス排出と資源循環の両面で重要なカギを握る分野です。
※1 参考:外務省「日本の排出削減目標」
2.カーボンニュートラルが注目される背景
2−1国際的な潮流 ― 脱炭素は「競争条件」へ
EUは「グリーンディール政策」※1により、2050年までの気候中立を法制化しました。
2026年から導入予定の「炭素国境調整メカニズム(CBAM)」※2により、EU域外企業もCO₂をはじめとした温室効果ガス排出に応じたコストを負担することになります。
米国・中国も大型投資を行い、「脱炭素を前提とした貿易・投資」の時代が到来しました。
この流れを受け、日本企業も取引先からのサプライチェーン排出量の報告を求められるケースが急増。
特に製造業や建設業、物流、廃棄物業界は、直接・間接双方で多くの温室効果ガスを排出するため、「排出を正確に把握・削減・オフセットできる企業」が今後の競争を優位に進むことができるのです。
※1 グリーンディール政策:EUが2050年のカーボンニュートラル実現に向けて進める、脱炭素と経済成長を両立させるための政策
※2 炭素国境調整メカニズム(CBAM):EUが導入を進めている、輸入品に含まれる炭素排出量に応じてコストを調整する制度
2−2 投資家・金融機関からの関心度
ESG投資の市場規模は世界で 30兆ドル を超え、今後10年の間にその5倍近くに拡大すると見込まれています。世界中の投資家層の中でESGの採用が急速に進んでおり、グローバルな資産配分戦略の核心的な存在になりつつある程、脱炭素経営を進める企業に資金が集まっています。
一方で、気候変動への対応を怠る企業は、サステナビリティに配慮したグリーン企業の逆である「ブラウン企業」としてリスク評価が高まり、資金調達や取引継続に不利な立場に立たされることも少なくありません。今やTCFD(気候関連財務情報開示タスクフォース)※3やSBTi(科学的根拠に基づく目標設定)※4など、グローバル基準に沿った排出量管理と情報開示がマストに求められる時代です。
※3 TCFD:気候変動リスクを財務情報として開示するための国際的枠組み
※4 SBTi:企業の温室効果ガス削減目標を国際基準で認定する仕組み
3.カーボンニュートラルに取り組む企業側のメリット
3−1経営リスクの低減とESG評価向上
脱炭素経営を推進することで、法規制・炭素コスト・評判リスクなどを事前に回避できます。
また、ESG格付けやサステナビリティレポートでの評価向上は、投資家・取引先との信頼強化に直結します。
3−2コスト削減と業務効率化
エネルギー効率改善や廃棄物削減、輸送ルート最適化など、脱炭素施策はそのままコスト削減につながります。
たとえば、イーコスが支援した製造業のクライアントでは、従来無料回収となっていたプラパレやプラコンテナを有価物として買い取るスキームを構築し、年間約35万円の実質的な利益改善を実現しました。
3−3企業ブランドと採用力の強化
消費者や求職者が「環境に配慮する企業」を重要視する風潮は年々強まっています。脱炭素経営を公表することは、企業イメージを高め、サプライヤー選定で優位に立つだけでなくZ世代を中心とした優秀人材の獲得にも寄与します。
4.カーボンオフセットの導入
GHG削減努力を尽くしても、ゼロにはならない残余排出(Residual Emission)が存在します。これを補う手段が「カーボンオフセット」※1です。
カーボンオフセットの主な目的は、温室効果ガス削減を加速させ、急速に進行している地球温暖化を抑制することです。カーボンクレジット(J-クレジット※・ボランタリークレジット※など)を購入し、自社の排出分を環境価値で相殺(オフセット)することで、実質的なカーボンニュートラルを達成できます。
具体的な導入方法としてはまず「事業活動によってどれくらいの温室効果ガスが排出されているのか」を算出することが重要になります。イーコスでは、廃棄物由来の排出量を算定した上で、「どの範囲を削減し、どの範囲をオフセットすべきか」という最適設計をサポートします。
※1 カーボンオフセット:削減しきれない温室効果ガス排出量を、他の場所での排出削減・吸収量によって埋め合わせる仕組み
※2 Jクレジット:日本国内の省エネや再エネ導入、森林管理によるCO₂削減・吸収量を、国が「クレジット」として認証する制度
※3 ボランタリークレジット:国の制度ではなく、民間主導で創出・取引されるCO₂削減・吸収量のクレジット
日本におけるカーボンオフセットの主な取り組み
1.オフセット製品やオフセットサービスの利用
あらかじめ事業者が製品の製造や流通、廃棄時やサービス提供、購入時などに発生する温室効果ガス排出をオフセット
2.会議やイベントにおけるオフセット
国際会議や大規模イベントなど、主催者が催事を開くことで発生する温室効果ガス排出量をグリーンクレジット※を購入するなどしてオフセット
3.自己活動オフセット
自分たちの団体や組織の事業活動を行う中で、事業所で使用する電気や、通勤や勤務中の移動、出張などに伴って排出される温室効果ガスをオフセット
4.寄付型オフセット
売り上げの一部をカーボンオフセットのためのクレジット購入に充てることを前提として、製品やサービスを販売することで消費者がそれらの購入や利用を通してカーボンオフセットに参画
もちろん企業だけではなく、個人でも温室効果ガス削減やオフセットを行うことは可能です。
カーボンニュートラルを実現するには、政府や企業だけの取り組みではなく、個人レベルでのライフスタイルの見直しも必須です。未来の地球を安心して暮らせる環境にするためにも、一人ひとりが普段から環境に配慮し、できることから行動に移していくことが大切です。
5.具体的な実践ステップ
脱炭素経営を進めるには、現状の把握から改善、発信までを一貫して進めることが重要です。以下の5つのステップで取り組みを整理することで、無理なく継続的な改善を実現できます。
- 現状把握
まず、廃棄物・エネルギー・輸送など、Scope1〜3における温室効果ガス排出量を算定します。
排出源を正確に把握することで、削減すべき重点領域を明確にできます。 - 削減計画
算定結果をもとに、削減効果(インパクト)と実行のしやすさ(実現可能性)の両面から優先度を設定します。
現場の実態に即した現実的なアクションプランを立てることがポイントです。 - 実行・可視化
設定した計画に基づき、エネルギー利用などのデータを定期的に収集・分析します。
排出量の変化を可視化することで、改善効果を定量的に確認できます。 - オフセット
削減努力だけでは抑えきれない排出分については、カーボンクレジットなどを活用して相殺します。
自社の削減目標に対して柔軟に対応できる仕組みを整えることが大切です。 - 開示・発信
取り組み成果は、ESG・統合報告書や自社ウェブサイトなどで開示します。
透明性の高い情報発信が、投資家や顧客からの信頼につながります。
これらのステップを通じて、企業は自社の排出構造を把握し、計画的かつ継続的に脱炭素経営を推進することができます。
6.まとめ
カーボンニュートラルへの対応は、義務ではなく新たな価値創造のチャンスです。特に廃棄物業界は、温室効果ガス削減・再資源化を通して「環境×経済」を結ぶ重要な存在です。
排出される温室効果ガス排出量を正しく把握し、削減に向けた取り組みを行なった上で、余剰分についても埋め合わせを行う。安心して暮らせる環境づくりのために脱炭素を「負担」ではなく「戦略」として捉える企業が、これからの市場で選ばれていきます。
イーコスでは、Scope算定の代行や、廃棄物に関する一次データを効率的に収集できるシステムの提供を通じて、事業場で発生する廃棄物課題の解決を支援しています。脱炭素経営や廃棄物管理の最適化をご検討の際は、ぜひ一度ご相談ください。
カテゴリー別に記事を探す
キーワード別に記事を探す
CONTACT
お問い合わせ
廃棄物の処理・管理、
資源の再利用に関する課題をお持ちの企業様
まずはお気軽に
お問い合わせください
まずは貴社の課題をお聞かせください。最適なプランをご提案をさせていただきます。
無料でお見積りも承ります。