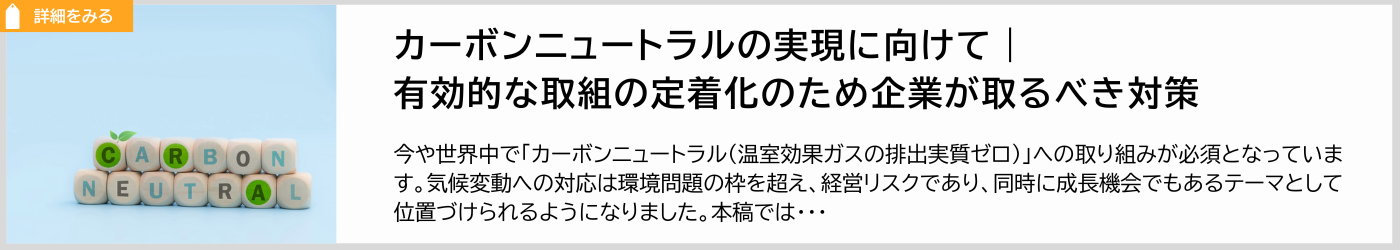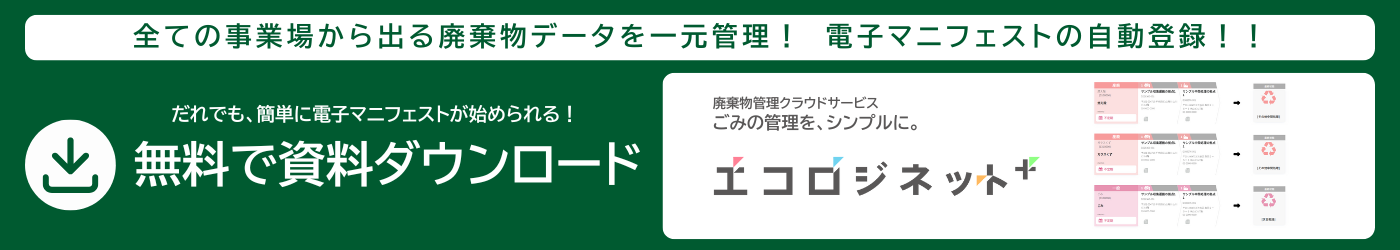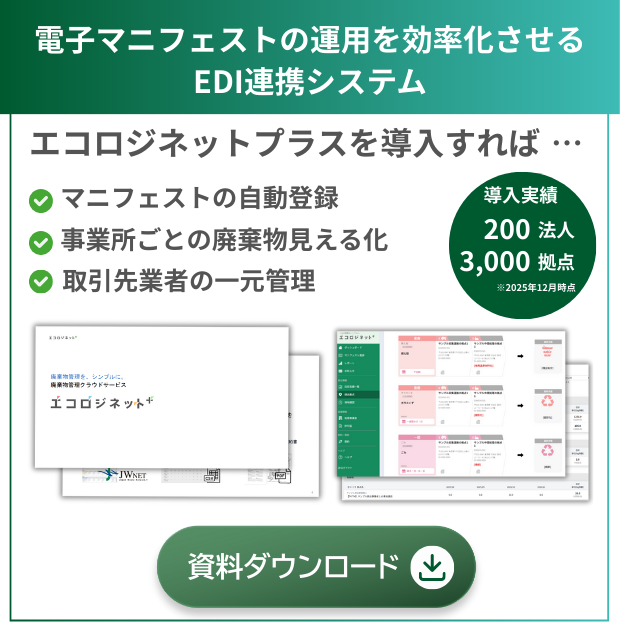エネルギーも“使い捨ての時代”から、“循環の時代”へ
いま、世界はエネルギーの大転換期にあります。化石燃料を大量に消費して成長を続けてきた20世紀型の経済モデルは限界を迎え、世界的に「グリーンエネルギー(再生可能エネルギー)」を中心とした新たな社会モデルへの移行が迫られています。
2025年上半期、世界の電源構成に占めるグリーンエネルギーの割合が初めて石炭を上回りました※1。
日本政府は2050年カーボンニュートラルの実現を掲げ、2030年までに発電電力量の 36~38%を再エネで賄うという目標を設定しました。企業や自治体、そして地域社会においても、「エネルギーの脱炭素化」が今や共通の課題です。
こうした変化の中で注目されているのが、太陽光・風力・水力・バイオマス・地熱・水素などのグリーンエネルギーです。これらは単なる電力供給手段にとどまらず、「循環型社会」「地域創生」「企業価値向上」を同時に実現する可能性を秘めています。
この記事では循環型社会を形成していく上で企業の新たな責任の一つである、グリーンエネルギーについて解説します。
※1 参照:Ember(環境・エネルギー分野の英シンクタンク)「Global Electricity Mid-Year Insights 2025」
目次
1.グリーンエネルギーとは ― “再生し続ける力”を活かす
グリーンエネルギーとは、自然界の循環の中で再生可能なエネルギーを指します。
太陽光、風力、水力、地熱、そして生物資源を燃料とするバイオマスなど、いずれも地球の自然サイクルの中で再び生まれる“持続可能なエネルギー”です。
一方、石油や石炭、天然ガスといった化石燃料は、一度使用すれば二酸化炭素を排出し、再生までに数百万年を要する「有限の資源」です。気候変動への悪影響といった環境負荷だけでなく、国際的な資源価格変動や地政学リスクにも直結しています。
グリーンエネルギーへの転換は、「環境負荷の軽減」だけでなく「エネルギーの安全保障」や「企業の経営安定性」にも関わるテーマです。
2.主なグリーンエネルギーの種類と特徴
2–1.太陽光発電 ― 最も身近で拡張性の高い再エネ
太陽光発電は、カーボンニュートラルを実現するグリーンエネルギーとして最もポピュラーな存在です。
枯渇する事のない太陽の光を直接電気に変えるため、環境に優しく気候変動に配慮したエネルギーです。
特に注目すべきは、企業の自家消費型太陽光発電です。
再エネ電力を自社施設で生み出すことで、電気料金の削減と同時にGHG排出の抑制にもつながります。現在では設置コストの低下や蓄電技術の進化により、工場やオフィス、住宅など、あらゆる場所で導入が進んでいます。
天然ガスや石油等とは異なり、海外から原料を輸入する必要がないので電力市場価格の影響を受けにくいというメリットもあります。
当社のクライアント企業でも、廃棄物処理施設や中間処理場の屋根を活用した太陽光導入事例が増えています。
“処理場がエネルギーを生み出す拠点へ”―これこそ、循環型経営の象徴といえるでしょう。
2–2.風力発電 ― 地域に「風の資産」を生かす
風力発電は、風の力を回転エネルギーに変えて発電する方式です。大型化・高効率化が進み、特に沿岸部や山間地域では高い発電量を誇ります。また、近年は洋上風力発電の開発も進み、政府は「2040年までに導入容量3,000万〜4,500万kW」を目標に掲げています。※2
風力は昼夜問わず発電可能な上、エネルギー返還率が他のグリーンエネルギーよりも高く、発電コストが比較的安価な点も特徴です。
地域にとって風力発電は、単なる再エネ導入だけでなく、地元雇用や地域経済の活性化にもつながります。
風力設備の保守・点検・関連産業の誘致により、地方が「再エネ産業の拠点」として再生する事例も増えています。
※2 参考:経済産業省 「浮体式洋上風力発電に関する国内外の動向等について」
2–3.水素エネルギー ― “燃やしても水になる”究極のクリーンエネルギー
水素は燃焼してもCO₂を排出しない、究極のゼロエミッション燃料です。
エネルギー効率が高く貯蔵できるエネルギーとして、主に発電や燃料電池自動車や船舶などの産業用途にて活用されています。
しかし、現状ではその製造過程において化石燃料が使用されています。
そのため、近年注目されているのが「グリーン水素」です。
これは再生可能エネルギーを用いて水を電気分解し、水素を生成する方式で、真にカーボンフリーなエネルギーといえます。
将来的には、再エネの貯蔵・輸送手段としても重要な位置を占めることが期待されています。
2–4.バイオマスエネルギー ― “廃棄物”を“資源”に変える力
木材、食品残渣、家畜排せつ物、廃食油などの生物由来資源を燃料にしてエネルギー化する仕組みで、廃棄物処理とエネルギー創出を両立できます。
バイオマスエネルギーは、使用すればGHGを排出しますが、GHGを吸収して成長する木材などを材料として使っていることから、全体的に見ると大気中のGHG量には影響を与えない「カーボンニュートラル」です。
主に木質(木材チップ、薪等)系バイオマス、廃棄物(生ごみ、農業等)系バイオマス、液体燃料(バイオエタノール等)系バイオマスがあり、これらは基本的に天候にも左右されず安定供給が可能で、廃棄物の活用手段としても有効です。
また、バイオマスエネルギーは気候変動への対策だけでなく雇用の創出や地域の賑わい創出にも貢献しますが、太陽や風、水のエネルギーとは異なり、バイオマス燃料を栽培・収集・加工・輸送する際にコストがかかるというデメリットがあります。
当社では、産業廃棄物の再資源化支援を通して、バイオマス燃料の原料となる有機廃棄物の安定供給をサポートします。
「廃棄物からエネルギーを生む」という、まさにグリーンエネルギーの循環を支える役割を担います。
3.企業がグリーンエネルギーに取り組む理由
3–1.ESG・TCFD時代の“説明責任”
企業が自らの事業活動による温室効果ガス排出を算定・開示し、削減への取り組みを示すことは、今や投資家からの当然の要求となっています。
再エネ利用率の向上は、ESG評価・SBT認定などの指標にも直結します。「どのようなエネルギーを使っているか」「再エネ比率をどのように増やしているか」という情報は、企業価値を測る新たな“信頼指標”となりつつあります。グリーンエネルギーを積極的に活用する企業は、顧客・取引先・社員から高い信頼を得やすくなります。
また、若年層は「環境に配慮した企業」を選ぶ傾向が強く、グリーンエネルギーへの投資は採用広報・企業ブランディングの要素としても有効です。
3–2.コスト・リスク両面の合理化
一見、再エネ導入はコストがかかるように思われますが、長期的に見れば電力価格の安定化・脱炭素コストの削減という大きな経済効果があります。
さらに、電力の地産地消モデルによって災害時のレジリエンス強化にもつながります。
企業がエネルギー源を多様化させることは、不安定な国際情勢や原料高騰の影響を受けにくくする“リスク分散”の意味でも重要です。
3–3.政策・市場の変化
政府は、グリーンエネルギーを最大電源と定め、GHG排出に対して企業に金銭的負担を求める方針に転換しています。
今やグリーンエネルギーは、環境対策にとどまらず企業のコストや競争力に直結するテーマです。
世界情勢によるエネルギー資源の高騰、そしてGHG排出削減が世界的な公約となる中、天然資源の乏しい日本ではグリーンエネルギーを最大限活用することがカーボンニュートラルな社会を実現する上で重要です。
4.廃棄物業界×グリーンエネルギー ― 当社が描く循環型モデル
当社は、企業の廃棄物管理・GHG削減支援を通じて、「廃棄物から新たなエネルギーを生み出す」循環型ソリューションを推進しています。
(1)排出データの見える化
電子マニフェスト・DXを活用し、拠点ごとの廃棄物排出量やGHG排出量を可視化。
エネルギー転換可能な有機廃棄物を特定し、グリーンエネルギー利用へとつなげます。
バイオマス発電事業者やリサイクル企業との連携により、「廃棄物→燃料→電力」というサイクルを形成。
企業にとっては、廃棄コストの削減と同時に、グリーンエネルギー創出への貢献が可能になります。
(3)グリーン電力・カーボンクレジットの活用
自社でグリーンエネルギーの導入が難しい企業には、グリーン電力証書やカーボンクレジットを組み合わせたオフサイト型の脱炭素戦略を提案。実質的な再エネ率の向上を支援します。
5.今後の展望 ―「エネルギーの地産地消」と「共創型サステナ経営」
今後の企業エネルギー戦略のカギは、「地域と共に創る共創型再エネモデル」です。
地元の再エネ事業者や自治体、教育機関・NPOと連携し、地域資源を活かしたエネルギー循環を構築することで、地域経済の活性化にもつながります。
たとえば、地域の廃棄物をバイオガスに変え、得られた電力を地元の公共施設や工場に供給する――
そんな「環境と経済を両立する地域エコシステム」の実現が今後さらに求められてくるでしょう。
6.まとめ ― グリーンエネルギーは“未来への投資”
グリーンエネルギーは、コストではなく未来への投資です。
エネルギーを「使う」だけの企業から、「生み出し、循環させる」企業へ。この転換こそが、持続可能な社会を実現する第一歩です。
当社は、廃棄物の適正処理と再資源化、GHG排出の可視化、効果的なグリーンエネルギーの利用促進を通して、企業の脱炭素経営を支援していきます。
限りある資源を活かし、次世代へとつなぐ――
それが、当社が目指す「サステナブルな社会づくり」です。
カテゴリー別に記事を探す
キーワード別に記事を探す
CONTACT
お問い合わせ
廃棄物の処理・管理、
資源の再利用に関する課題をお持ちの企業様
まずはお気軽に
お問い合わせください
まずは貴社の課題をお聞かせください。最適なプランをご提案をさせていただきます。
無料でお見積りも承ります。