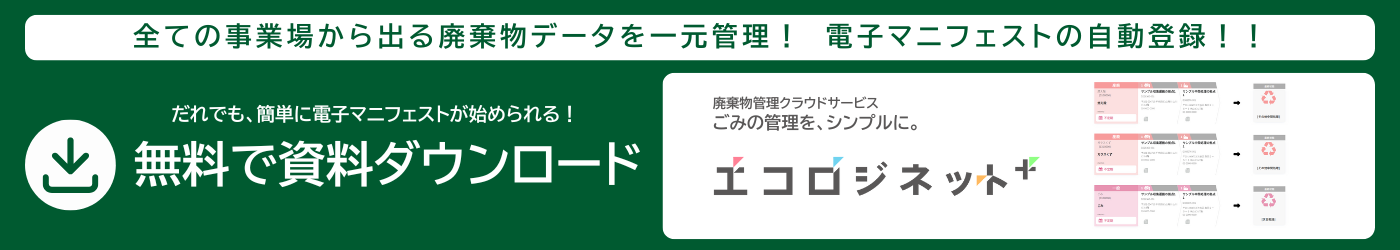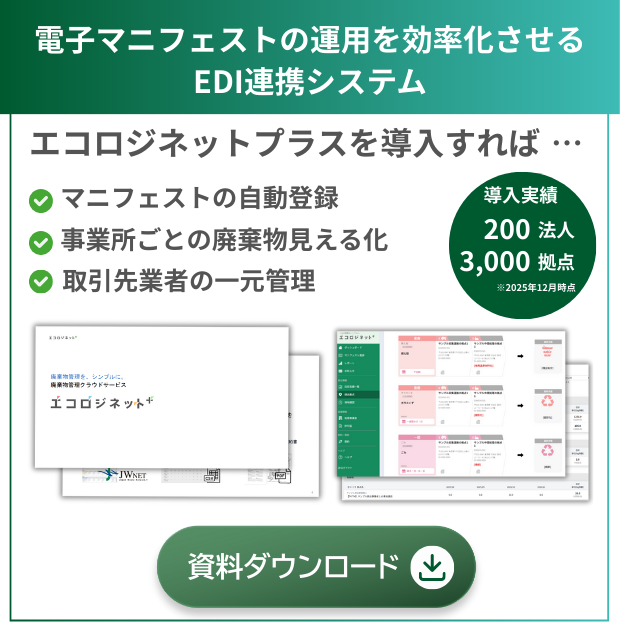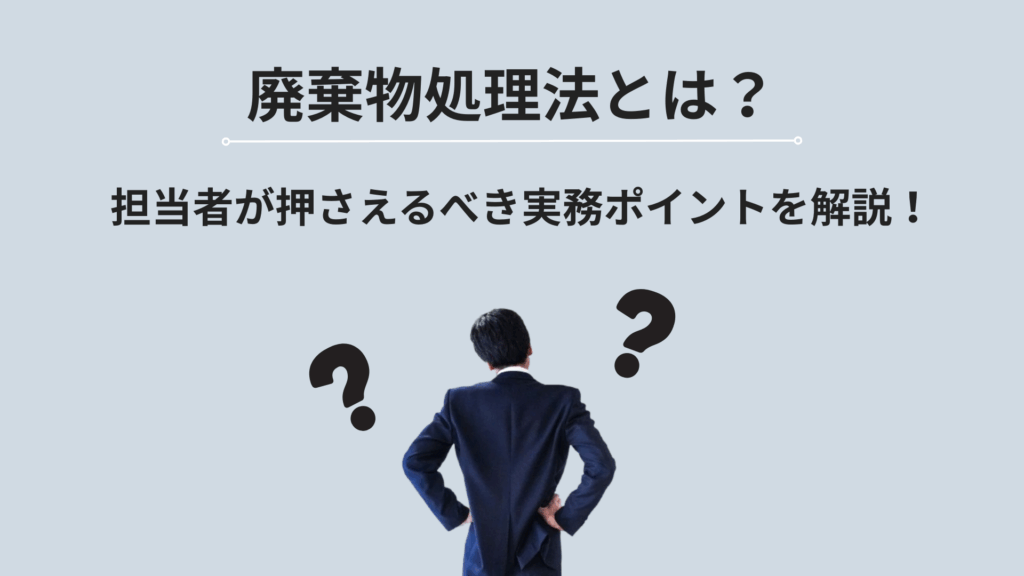
マニフェストとは?廃棄物を適正管理するマニフェスト制度と運用方法を解説!

廃棄物を適正管理するマニフェスト制度と運用方法について
マニフェスト(産業廃棄物管理票)は、排出事業者が産業廃棄物の処理を委託する際に処理業者(収集・運搬業者、中間処理業者)へ、交付しなければならない伝票のことです。
高度経済成長期、モノの大量生産・大量消費が進み廃棄物の排出量も急増しました。それに伴い、日本各地で不法投棄や廃棄物の不適正処理が発生し大きな社会問題となりました。このような背景を受け、1993年に特別管理産業廃棄物のマニフェスト義務化、1998年にすべての産業廃棄物にマニフェストの使用が義務付けられました。ここでは、マニフェスト制度について解説していきます。
目次
マニフェストとは
マニフェスト(産業廃棄物管理票)は、廃棄物を処理業者に引き渡した後、契約通りに処理されているかを確認する伝票です。産業廃棄物を排出する排出事業者は、廃棄物の処理を委託する場合、処理業者へマニフェストを交付しなければならないと義務付けられています。マニフェストには廃棄物の種類や数量、運搬業者、処理業者の情報が記載されており処理が完了するまで廃棄物とともに移動します。
1993年に特別管理産業廃棄物のマニフェスト使用が義務化された際は、複写式の紙のマニフェストの運用でしたが、1998年にすべての産業廃棄物にマニフェストの使用が義務付けられてからは電子マニフェストの導入もスタートしました。紙のマニフェストも電子マニフェストも排出事業者が交付するもので、その記載内容に違いはないものの運用方法については、大きな違いがあります。
マニフェストの種類
マニフェストには、紙のマニフェストと電子マニフェストの2種類があります。 紙のマニフェストは、7枚つづりの複写式のもので運搬、中間処理、最終処分が完了した各過程で排出事業者にマニフェストが返送されます。 一方、電子マニフェストとは、公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センターが運営する、電子マニフェストシステム(JWNET)です。排出事業者はJWNETに情報を入力し、委託を受けた処理業者はJWNETに完了報告をすることで適正に管理をすることができます。 具体的な運用方法は、下記のとおりです。
紙のマニフェスト
紙のマニフェストは7枚つづり(A票、B1票、B2票、C1票、C2票、D票、E票)の複写式伝票です。 排出事業者は廃棄物の種類や数量、委託先業者などを記載しA票以外を運搬業者に渡します。 委託を受けた処理業者は、処理が完了した段階で必要事項を記入し排出事業者に返送します。 すべての処理が完了すると、A票、B2票、D票、E票の4枚が排出事業者の手元に残りその内容に間違いがないかを確認し、これを5年間保管しなければなりません。
また、紙のマニフェストの場合、毎年6月30日までに前年度(4月1日から翌年3月31日まで)に交付したマニフェストの交付状況について、「産業廃棄物管理票交付等状況報告書」を作成し、所轄の都道府県知事または政令市長に提出する義務があります。
運用の流れ
- マニフェストの交付
マニフェストに必要事項を記載し、処理業者へ交付。 - 処理状況を管理
回収された廃棄物は、運搬、中間処理、最終処分完了の過程でマニフェストが返送されます。 このマニフェストは交付の日から5年間保管しなければなりません。
A票:引き渡し時に自社保管
B2票:運搬完了時に運搬業者から、必要事項が記載され返送される
D表:中間処理完了時に中間処理業者から、必要事項が記載され返送される
E表:最終処分が完了時に中間処理業者から、必要事項が記載され返送される - 行政への報告
毎年6月30日までに前年度の廃棄物の処理状況(産業廃棄物管理票交付等状況報告書)を作成し行政へ報告しなければなりません。
注意点
- マニフェストの記載ミスを防ぐ
記載内容に誤りがあると法令違反となるため、正確な情報を記入しなければなりません。
- 期日管理の徹底
B2票・D票・E票の返送状況を管理し、未回収がないか定期的に確認する必要があります。
※B2票・D票は交付の日から90日以内
※E票は交付の日から180日以内 - 保管と監査対応
マニフェストは5年間の保管義務があるため、監査の際はすぐ提示できるよう準備しておく。
電子マニフェスト
排出事業者は廃棄物の回収日が決まると、JWNETへ廃棄物の種類や数量、委託先業者などを入力します(電子マニフェストの登録)。 委託を受けた処理業者は処理が完了した段階でJWNETへ完了報告を行い、排出事業者は期限内に完了報告がされているかを確認します。処理業者の完了報告の期限は、運搬・処分が完了した日から3日以内とされており、排出事業者も同様に引き渡した日から3日以内にマニフェストの登録が必要です。(土日祝、年末年始は含まない)
また、電子マニフェストを利用している場合は、マニフェストの情報がシステム上に自動で蓄積されるため、産業廃棄物管理票交付等状況報告書の提出は不要です。
運用方法
- マニフェストの登録
JWNETへ必要事項を入力する。
※引き渡し日から3日以内 - 処理状況を管理
処理を委託した廃棄物が期限内に処理され完了報告がされているかを確認します。
※運搬完了報告:運搬が完了した日から3日以内
※処理完了報告:処理が完了した日から3日以内
注意点
- 登録ミスを防ぐ
電子マニフェストでは、契約情報や廃棄物の種類、処理業者の情報などを事前に登録する必要があります。入力に誤りがあると処理業者が入力できないなどトラブルが発生します。 - 処理状況の確認を定期的に行う
電子マニフェストの特徴は、処理の進捗状況をリアルタイムで確認できることです。適正な処理が行われているかを継続的にチェックすることが期限内に処理されているかを管理します。
電子マニフェストの導入
電子マニフェストは、電子マニフェストシステム(JWNET)へ登録することでIDとパスワードが発行され利用することができます。しかし、電子マニフェストの運用をはじめるには、システムに登録するだけでなく、処理業者との事前の調整や社内間の運用方法などを取り決めておく必要があります。電子マニフェストの導入前の準備は、下記のとおりです。
JWNETへの登録
電子マニフェストを利用するには、JWNETへの利用登録が必要です。登録にあたって、会社情報や担当者情報の入力が必要です。また、電子マニフェストの利用には、利用料が発生します。必要情報、登録するプランを選択後、ログインIDやパスワードが発行されシステムの利用が可能になります。
処理業者との調整
電子マニフェストの運用は、排出事業者と処理業者(収集・運搬業者、中間処理業者)がJWNETに登録しておく必要があります。導入を検討する際は、既存の処理業者が電子マニフェストの利用が可能かを確認し、対応していない場合は、委託先の検討をする必要があります。また、運用するにあたり、JWNETへの入力ルールや入力のタイミング、受渡確認票の準備など事前に打ち合わせておく必要があります。
社内調整
電子マニフェストの導入にあたって、社内で「いつ」「どの排出事業場から」電子に切り替えていくのかといった運用開始のルールを明確に決めておくことが重要です。具体的な方針を決めておかなければ、現場ごとの判断にばらつきが出て混乱の原因になります。また、JWNETへの情報入力や業者からの問い合わせは誰が対応するのか、社内の体制を事前に整えスムーズな導入体制を構築しましょう。
マニフェストは、排出事業者が適正に管理しなければならない重要な仕組みです。紙と電子の運用方法がありますが、ミス防止や業務効率化を考えると、電子マニフェストの運用がおすすめです。ただし、電子マニフェストの導入にはJWNETへの登録や処理業者との調整、社内間の調整など、いくつかの手順が必要です。弊社が提供するエコロジネットプラスは、JWNETと公式に連携したEDIシステムです。電子マニフェストの運用を正しく、簡単に行うことが可能なクラウドサービスですので、ご興味がある方は、ぜひお気軽にお問合せください。
カテゴリー別に記事を探す
キーワード別に記事を探す
CONTACT
お問い合わせ
廃棄物の処理・管理、
資源の再利用に関する課題をお持ちの企業様
まずはお気軽に
お問い合わせください
まずは貴社の課題をお聞かせください。最適なプランをご提案をさせていただきます。
無料でお見積りも承ります。